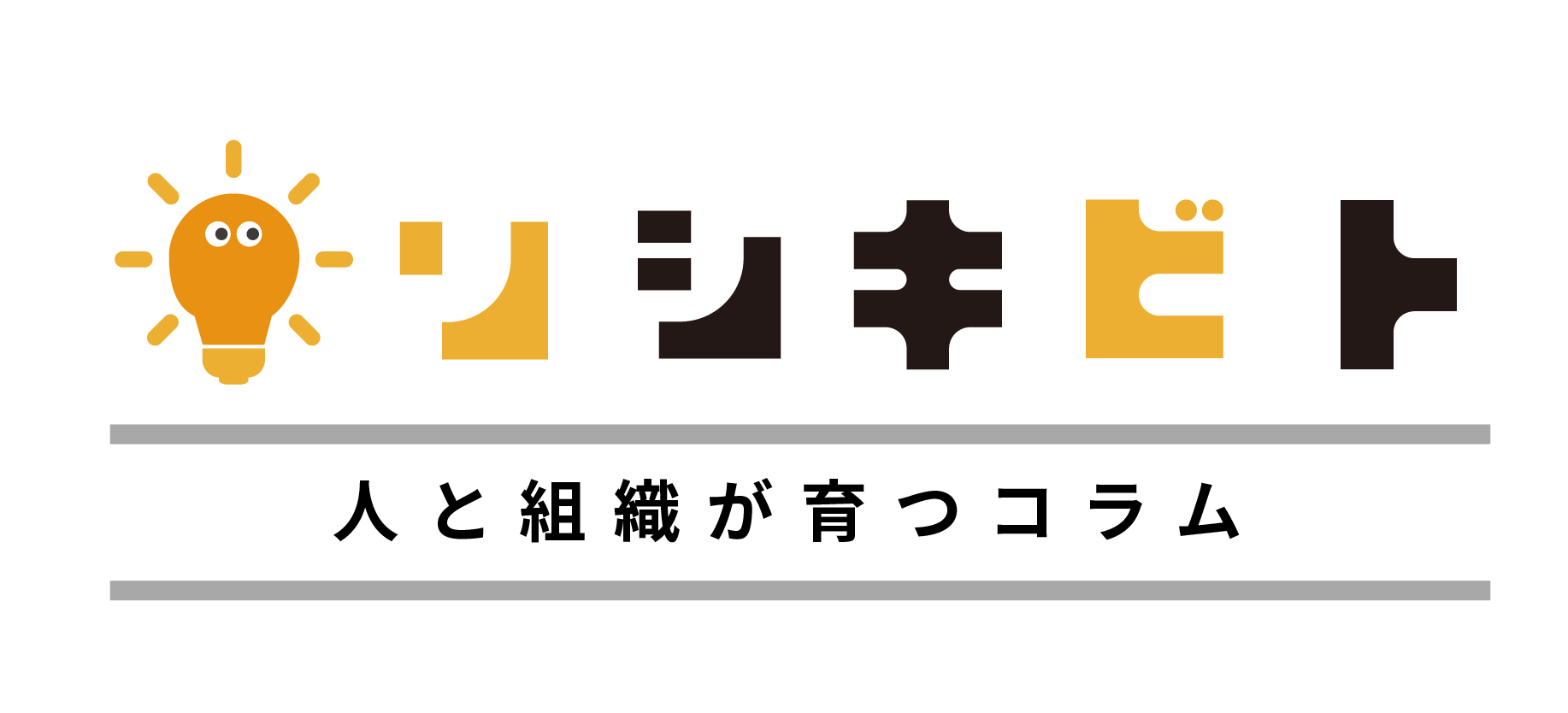働き方改革は、企業のみならず、社会的な関心事となっています。しかし、組織や労務に関する研究分野では、働き方改革に対する企業の取り組みのほとんどが残業時間の調整に重きが置かれており、狭義の働き方改革しか実践されていないことが課題として挙げられています。働き方改革のメインの目的は多様で柔軟な働き方を実現し、従業員一人ひとりが高い時間意識を持った働き方へとシフトすることにあります。本記事では、改めてこれまでの働き方の歴史、政府による働き方改革の各法案が目指すところについて詳しく解説していきます。
目次
働き方改革の歴史

2018年6月29日、「働き方改革関連法案」(正式名称「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」)が参院本会議で可決・成立しました。私たちがよく耳にする「働き方改革」は、この法案に基づく改革内容を指すことが多い。しかし、働き方を改革することに対する意識は、「働き方改革」という言葉が今ほど定着していない終戦直後から存在していました。
1945年、終戦直後の労働環境を象徴する動きのひとつとして、労働組合の結成が挙げられます。労働組合は第一に「食える賃金」を要求し、第二に「企業内民主化」を求めました。すなわち、「職員」や「工員」といった、企業内の身分差別の撤廃を要求したのです。
この要求により、戦後早い段階で「職工」や「労務者」などの差別的な用語が改められ、「従業員/社員」または「技能職」と呼ばれるようになりました。そして、彼らのようなブルーカラー労働者も厚生施設が利用できるようになり、家族手当、通勤手当、住宅手当、ボーナスの算定基準の格差が縮小されていきました。
高度経済成長期の日本では、働けば働くほど待遇が上がっていくようになり、睡眠時間を削ってまで働き、多忙でいることが生産的であると考える「モーレツ社員」という価値観が生まれました。
しかし、1991年のバブル崩壊後は、働いても働いても高度成長期ほどの待遇アップは見込めず、さらに不景気による人員削減によりこれまで以上に仕事量が増えてしまったこと、労働基準法を無視した違法なサービス残業が常態化したことで、過労による問題が顕在化しました。
その結果、2013年、日本は「多くの従業員が長時間労働をしている」「過労死やハラスメントによる自殺者が増えている」などの過労問題について、国連から是正勧告を受けてしまいました。
そして、2016年に内閣官房に「働き方改革実現推進室」が設置され、2018年に「働き方改革関連法案」が可決・成立し、2019年4月から「働き方改革関連法案」が順次施行されていきました。
「働き方改革」が目指すところ

働き方改革とは、これまでの労働問題を解決し、生産労働人口が減少している日本において、「働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会」を実現することを目指しています。
厚生労働省は、「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて 〜」の中で、働き方改革について以下のように言及しています。
「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
「働き方改革関連法案」のポイント1:労働時間法制の見直し

「働き方改革関連法」の中では、過労を防止し、ワークライフバランスと多様で柔軟な働き方を実現することを目的として、労働時間法制が見直されました。
残業時間の上限規制
既存の労働基準法では、「労働時間は1日8時間、1週間40時間が原則」となっているものの、36協定のもとでは「原則として1ヶ月45時間、1年間360時間」まで、企業は労働時間を延長できていました。つまり、法律上は、残業時間の上限がなく、超えた場合は行政指導のみ(※1, p. 4)ということになっていました。
これに対し、「働き方改革関連法案」では、「原則として1ヶ月45時間、1年間360時間」に加え、臨時的な特別な事情がある場合かつ労使が合意する場合においても、年間720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、復数月平均80時間(休日労働含む)を限度として法律で定め、違反した企業には罰則が設けられました。
「勤務間インターバル」制度の導入促進
勤務間インターバル制度とは、終業から始業までの間に、労働者が一定時間以上の休息時間を確保できるようにすることを目的とした制度です。労働者が休息時間を確保できることで十分な睡眠だけではなく、プライベートに費やす時間を増やし、ワークライフバランスの向上を目指しています。
既存の「労働時間等設定改善法」(労働時間等の改善に関する特別措置法)が改正されることで、勤務間インターバル制度が設けられました。2019年4月1日より施行され、勤務間インターバル制度は努力義務とされています。
厚生労働省では、終業から次の始業までのインターバル時間として9〜11時間以上を推奨しています。厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、勤務間インターバル制度を導入している企業事例が80件以上紹介されています。
年5日の年次有給休暇の取得
既存の労働基準法では、6ヶ月以上連続勤務し、全労働日の8割以上を出勤した労働者に対し、10日の有給休暇を付与することが義務付けられています。今回の改正では、年10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対し、5日間有給休暇を取得させることが義務となりました。
有給を取得させることが義務付けられた背景としては、多くの日本企業で労働者が有給休暇を申請しにくいという問題があったからです。厚生労働省によると、日本の年休取得率は51.1%ほどしかないそうです(※1, p. 10)。
このような状況を踏まえて、今回の法案では、企業から労働者に有給休暇の希望を聞き、希望を踏まえて労働者が有給休暇を取得する時季を企業が指定することが求められています。
月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げる
月60時間を超える残業に対し、企業は労働者に割増賃金を支払うことになっていましたが、割増賃金率が企業規模によって異なりました。具体的には、大企業では50%、中小企業では25%とされていました。しかし、法改正後は中小企業も割引賃金率を大企業と同じ50%に引き上げられました。
| 1か月の時間外労働 (1日8時間・1週40時間を超える労働時間) | ||
| 60時間以下 | 60時間を超 | |
| 大企業 | 25% | 50%(変更なし) |
| 中小企業 | 25% | 25%(改正前) → 50%(改正後) |
労働時間の状況を客観的に把握する
「働き方改革関連法案」の施行前までは、割増賃金を適正に払うことを目的とし、労働者の労働時間を客観的に把握するように通達されていました。そのため、裁量労働制で働いている労働者は、労働時間の客観的把握の対象外でした。
改正後は、労働者の健康を確保するという観点から、裁量労働制が適用されている労働者や管理監督者含め、全ての労働者の労働時間の状況を客観的な方法で管理し、把握することが法律で義務付けられるようになりました。
「フレックスタイム制」の拡充
これまで、労働時間の精算期間は1ヶ月とされていました。例えば、労働者が4月は残業して多く働き、6月は所定労働時間より短く働いたとします。労働時間の精算期間が1ヶ月の場合、企業は4月は労働者に割増賃金を適用した残業代を支払い、6月は所定労働時間未満のため、足りない分を欠勤扱いとすることになります。
しかし、改正によって労働時間の精算期間が3ヶ月となりました。そのため、上記のケースの場合、企業は4月に割増賃金を支払う必要がなくなり、労働者が4月に多く働いた分を6月の所定労働時間未満の月に振り替え、欠勤ではなく出勤扱いとすることができます。
この改正により、労働者は子育てや介護などの生活サイクルに合わせて計画的に労働時間を決めて、柔軟な働き方を実現することが可能となります。
「高度プロフェッショナル制度」を新設
「高度プロフェッショナル制度」とは、高度な専門知識を必要とする厚生労働省が指定する対象業務を遂行し、一定の要件を満たす労働者に対し、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置を講ずることで、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。
本制度が適用される労働者かどうか判断するにあたって、以下の厚生労働省が定める要件を満たしているか確認する必要があります。
【対象者】
- 使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること
- 使用者から確実に支払われると見込まれる1年間当たりの賃金の額が少なくとも1,075万円以上であること
- 対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが原則であり、対象業務以外の業務にも常態として従事している者は対象労働者とはならないこと
【業務内容】
対象業務に従事する時間に関して使用者から具体的な指示を受けて行うものではないことが必須となっています。本制度が適用される具体的な対象業務は以下の通りです。
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
- 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
- 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
- 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
※厚生労働省「⾼度プロフェッショナル制度わかりやすい解説」より抜粋
「産業医・産業保健機能」を強化
「働き方改革関連法案」では、長時間労働やハラスメントなどによる健康リスクの高い労働者を企業が見逃さないために、企業と産業医の連携を強化し、面談指導や健康相談を確実に実施できる状態の実現を目指しています。
これまで、企業は産業医が労働者の健康確保のために必要と判断した情報のみを提供する仕組みとなっていましたが、今後は企業側から産業医が労働者の健康管理に必要と思われる、長時間労働の状況や業務の状況を提供しなければならなくなりました。
また、企業は産業医から労働者の健康について勧告を受けた場合は、衛生委員会に報告することが義務付けられました。
「働き方改革関連法案」のポイント2:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

「働き方改革関連法案」では、雇用形態の違いによる不合理な待遇差をなくし、雇用形態の待遇に納得して労働者が働き続けられるようにすることを目指しています。これにより、労働者は雇用形態に縛られることなく、自身のライフスタイルや価値観にあった働き方を選択できるようになります。
不合理な待遇差の禁止
法改正後は、同一企業内において、正規雇用の社員と非正規雇用の社員の間の基本給や賞与などの待遇にて不合理な差を設けることが禁止となりました。特にその中でも「同一労働同一賃金」が注目されています。
厚生労働省によると、非正規雇用の社員の時間あたりの賃金は正規雇用の社員の60%程度と言われています。しかし、近年は技術の発展やライフスタイルの変化により、日本人の働き方が多様化しており、非正規雇用の社員が占める割合は約40%まで増えました。
そのため、正規雇用の社員と非正規雇用の社員の間に格差があると、組織の中で一定の割合を占めている非正規雇用の社員の不満が募り、生産性が低下してしまうことが懸念されます。このままでは企業だけではなく、日本全体としても失速してしまうため、雇用形態に関わらず、同じ内容の仕事をしている労働者には、同一の賃金を対価として支払うことが義務付けられました。
待遇に関する説明義務の強化
「働き方改革関連法案」の施行により、企業は非正規雇用の社員に対して、正規雇用の社員との待遇差の内容や理由について説明をすることが義務付けられました。また、非正規雇用の社員は待遇差について企業に説明を求める権利を持ち、企業は非正規雇用の社員が説明を求めたことによって不利益な扱いをすることは禁止されています。
行政による事業主への助言・指導等等の整備
行政ADRとは、非正規雇用の社員の保護を目的とした、行政による履行確保措置や裁判外紛争解決手続の規定を指します。今回の法案では、これまでの行政ADRが整備・強化されるだけではなく、その対象が非正規雇用の社員だけではなく、正規雇用の社員まで拡張されました。
働き方改革の目的を理解し、「働きがいのある職場」を作る

「働き方改革関連法」の内容は、雇用制度や評価制度に携わる人にとって業務上必須の知識のため、決まりごととして知っている人は多いでしょう。しかし、雇用制度や評価制度などについて現場に理解・納得してもらい、組織内においてスムーズに導入していくためには、ミドルマネジャーにも「働き方改革関連法」のその目的に関する知識をつけてもらうことが重要です。そのため、ルールに従うだけではなく、その背景と改正前後の違いについて人事から現場へと明確に説明できるように備えておくといいでしょう。
また、従業員が会社の待遇に満足しているかどうか知るためには、対面でのヒアリングや満足度調査、エンゲージメント調査が役立ちます。従業員がどのような点について不安や不満を持っているか把握することで、制度の改善だけではなく、なぜこのような制度になっているのか改めて説明する機会を設けるかどうかの判断にも繋がります。ぜひこれらのツールも貴社の「働き方改革」にてご活用ください。
【参考資料】
- ※1:厚生労働省. 「働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて 〜」
- 厚生労働省.「⾼度プロフェッショナル制度わかりやすい解説」
- ※労務理論学会誌編集委員会. 「働き方改革と『働きがい』のある職場」. 労務理論学会, 2019
- ※佐藤博樹, 武石恵美子. 「シリーズ ダイバーシティ経営 働き方改革の基本」. 中央経済グループパブリッシング, 2020