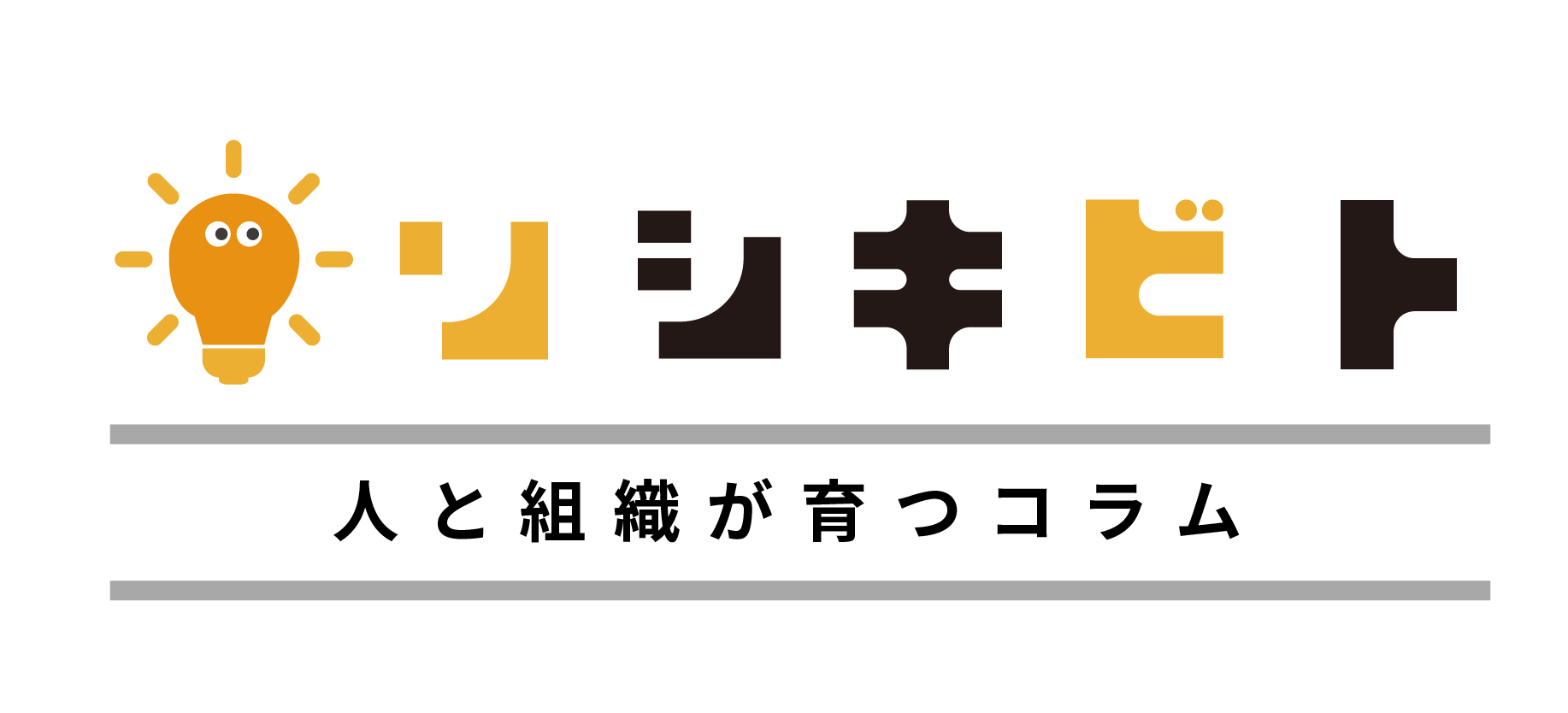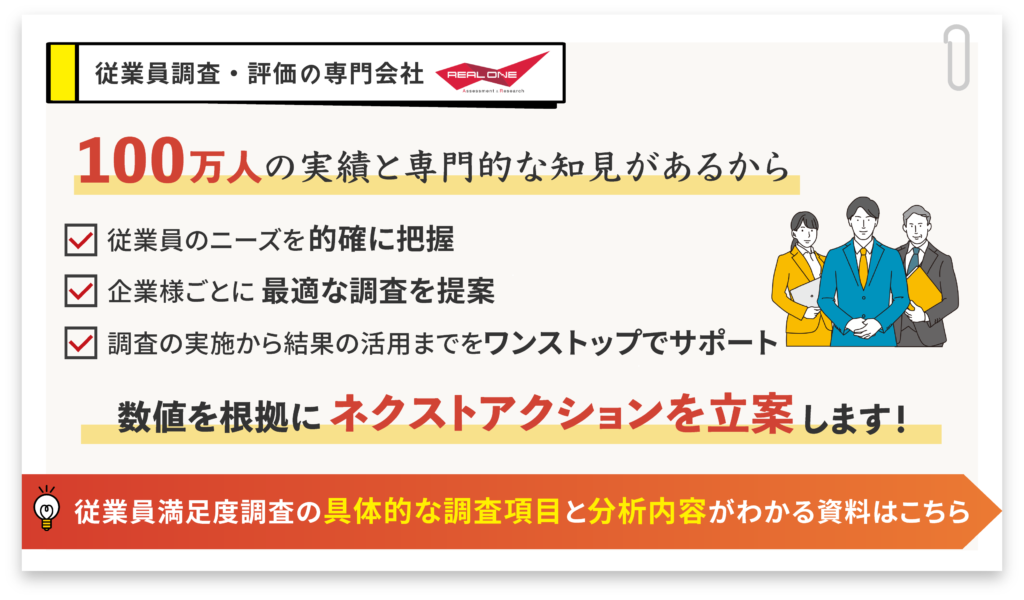従業員満足度アンケート(ES調査)は、従業員や組織の状態を把握できる信頼性のあるツールです。明確になった課題を改善することで、従業員満足度の向上はもとより、エンゲージメントや顧客満足度の向上も期待できます。ただそのためには、アンケートの目的を理解し可視化された結果を施策に落とし込む必要があります。本記事では、従業員満足度アンケートの目的を解説すると共に、何が可視化され、そしてそれをどう活用していくのかを考察します。
本記事は、従業員満足度アンケートを検討(実施)している、次のような人事関係者に役立ちます
- 従業員満足度アンケートで可視化されるものを知りたい
- 目的を理解したい
- 活用方法を知りたい
- 具体的にどのような改善に取り組めばいいのか理解したい
※従業員満足度アンケートがうまくいかない原因を知りたい方は、「コチラの記事」をご覧ください。
「従業員と組織の現状を可視化する」従業員満足度アンケート(ES調査)とは

まずは、従業員満足度アンケートについて整理してみましょう。
従業員満足度アンケートとは何か?
従業員満足度アンケートとは、従業員が仕事や職場にどの程度満足しているのか、またどのようなことに不満を感じているのかを可視化する調査のことです。選択式のアンケートに回答することで、従業員の状態を定量的に可視化し課題改善につなげていきます。従業員満足度の英訳「Employee Satisfaction」の頭文字をとって、ES調査とも呼ばれています。
従業員満足度アンケートの大きな特徴は、従業員の状態を定量的に可視化できることです。「仕事内容」「組織環境」「人間関係」「待遇」などのチェックから、従業員の仕事や組織の人間関・課題などを数値で表します。まさに、従業員と組織の「今」、「現状」を数値で可視化するツール。それが、従業員満足度アンケートなのです。
※従業員満足度アンケートについては、「コチラの記事」もご覧ください。
従業員満足度の重要性~重視される背景
従業員満足度は、なぜ重視されるのか。ここでは、その重要性を考察します。従業員満足度が重視される背景には、2つの大きな変化があります。ひとつは、「生産年齢人口の減少」、もうひとつは「従業員と組織の関係性のあり方の変化」です。詳しく見ていきましょう。
少子高齢化によって、日本の生産年齢人口は減少の一途を辿っています。このような状況にあっても、組織が競争力を維持していくためには、優秀な人材の確保が不可欠です。人材不足を補うため、DXによる業務の効率化は必要でしょう。しかし、DXを進めていくのも人材に他ならないのです。優秀な人材の確保は、今や企業の生命線です。
加えて、従業員と組織の関係性が「相互依存型」から「自律対等型」へと変化しています。従業員は、自律的にキャリア形成に取り組み「エンプロイアビリティ(雇用されうる能力)」を高めようとしているため、組織としても、従業員の自律的キャリア形成を後押しする関係性へと変わりつつあるのです。「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン」「健康経営」「ウェルビーイング経営」「ワークライフバランス」といった施策も、「自律対等型」への対応の表れでしょう。
2つの大きな変化の中で、組織は従業員一人ひとりの価値観や意識を深く理解し、働く環境を整備することが求められています。それが従業員の満足度を高め、優秀な人材の確保につながっていくからです。従業員満足度が重視される背景には、このような時代の変化があるのです。
※エンプロイアビリティについては「コチラの記事」を、キャリア形成については「コチラの記事」をご覧ください。
厚生労働省も重視する従業員満足度
厚生労働省も従業員満足度について重視する見解を示しています。厚生労働省は、従業員満足度の向上に取り組む企業の調査を実施。「今後の雇用政策の実施に向けた現状分析に関する調査研究事業」の報告書で、次のように述べています。
・雇用管理改善の取組は、従業員の意欲・生産性向上・業績向上・人材確保につながる
・経営においては、「従業員満足度」と「顧客満足度」の両方を重視するのが重要
※どちらかだけでなく、両方を追求することの効果が高い・継続的に取り組むことが大事
文部科学省「今後の雇用政策の実施に向けた現状分析に関する調査研究事業」報告書
※継続的に取り組んでいる 企業で業績や生産性の向上、人事目標の達成度合いが高い
このように従業員満足度を高める取り組みは、企業価値の向上にとって極めて重要な施策であると、厚生労働省も重視しているのです。
従業員満足度アンケート(ES調査)の目的

従業員満足度アンケートは、どのような目的で行うのでしょうか。ここでは、その目的を解説します。
従業員の満足度向上
従業員満足度アンケートでは、客観的な数値で従業員の状態が可視化されます。「やりがい」や「モチベーション」といった内面的な部分は、面談や日々の取り組みを見ているだけでは正確に把握できないものです。アンケートによって、従業員の状態を計測し、数値の改善を図ることで従業員の満足度を向上させることができます。不満があっても、従業員は口に出しにくいもの。アンケートを通じた従業員の意識の把握は、従業員と組織の関係構築の上でも欠かせない取り組みのなのです。
組織が抱える課題の把握
従業員満足度アンケートは、従業員が組織のどのような部分に不満を感じているのかが把握できます。従業員の不満は、組織が抱える大きな課題です。不満の原因が明らかになれば、課題改善の施策を立案し行動に移すことができます。その繰り返しが、継続的な従業員満足度の向上につながり、PDCAサイクルの精度を向上させるのです。組織が抱える課題の把握は、従業員満足度を向上させる重要な足がかりとなるものなのです。
施策の立案や検証
従業員満足度アンケートによって、施策の立案や検証が可能になります。明らかになった課題は、「企業理念・ミッション・パーパス」の再構築、「経営戦略・中長期計画」の立案に活用できるでしょう。また、「評価制度・組織編成・教育研修」などの検証に役立てることもできます。「経験」や「カン」ではなく、客観的な数値による課題の把握が、中身の濃い立案や検証を可能にするのです。
経営指標として定点観測
従業員満足度アンケートの継続的な実施は、経営指標としての定点観測に活用できます。それは、組織全体の満足度と共に、各部署ごとの課題を数値で可視化できるからです。従業員満足度アンケートは、組織の「健康診断」ともいわれるように、継続的に行うほど大きな価値を持ってきます。アンケートの結果を経営指標に落とし込み、数値変化を定点観測することで、問題の深刻化を防ぎます。
従業員満足度アンケート(ES調査)の活用方法

従業員満足度アンケートは、どう活用するのかが重要です。ここでは、従業員満足度アンケートの活用方法を見ていきましょう。
課題の改善
従業員満足度アンケートの実施は、課題改善への始まりです。アンケートから見えてきた課題を、必ず改善につなげましょう。従業員満足度アンケートは、実施自体にメッセージ効果があるといわれています。アンケートを行うことで、「自分たちのことを大切にしてくれている」と、従業員に期待を抱かせることができるからです。改善ともなれば、「会社は変わろうとしている」というメッセージとなり、「自分たちも頑張ろう」と、モチベーションアップやエンゲージメントの向上につながります。課題の発見と改善はワンセット。意識しておきましょう。
従業員へのフィードバック
実施後は、従業員へのフィードバックを必ず行いましょう。仮にネガティブなアンケート結果であっても、フィードバックすることで、従業員満足度の向上に取り組む姿勢を示すことができます。フィードバックをせず「やりっぱなし」では、継続的な取り組みにおいて回答率の低下や有益な回答が得られない弊害を生みます。従業員満足度アンケートを実施したら、フィードバックを積極的に行う。信頼関係構築の上でも極めて重要です。
離職防止
従業員満足度アンケートは、離職防止策として積極的に活用します。アンケートの実施によって、従業員が組織に求めていることを知ることができます。従業員の思いを形にすることで、組織に対する満足度は向上していくでしょう。働きやすい職場、そして「やりがい」を感じられる職場では、従業員のモチベーションもアップします。組織のリアクションは、先述の通りメッセージ効果となり、「この会社で頑張り続けたい」「もう少し踏ん張ってみよう」という意識を醸成し、離職防止につながっていくのです。
継続的な実施による好循環の形成
従業員満足度アンケートを継続的に行うことで、「課題発見→施策立案→改善→従業員満足度向上→組織活性化」という好循環を形成できます。好循環の形成は、従業員のエンゲージメント向上や顧客満足度の向上にもつながるでしょう。エンゲージエントや顧客満足度との関係性を検証することで、成長に向けてのビジョン形成にも役立ちます。従業員満足度アンケートは「1回実施して終わり」ではなく、継続的に実施してこそ本当の効果を得ることができる取り組みなのです。
従業員満足度アンケート(ES調査)集計結果の分析

従業員満足度アンケートを行い必要な数値が集まったら、集計結果の分析に移ります。ここでは、集計結果の分析手法を紹介しましょう。代表的な分析手法は、次の5つになります。
- 基本統計量
- クロス集計
- 比較
- 偏差値
- 相関係数
従業員満足度アンケートは、組織が抱える様々な課題を可視化します。課題を改善するために、効果的な施策を立案するには、アンケートで示された数値を的確に読み解く分析手法に対する理解が必要です。専門の調査会社にアンケートを依頼するとしても、分析手法の概要を理解し組織の状況を的確に把握できるように、心がけておきましょう。
※分析手法の詳しい解説については、「コチラの記事」をご覧ください。
従業員満足度アンケート(ES調査)の成功事例

ここでは、従業員満足度アンケートを実施し、従業員満足度を向上させている成功事例として、企業の具体的な取り組みを紹介します。
ワークライフバランスの改善
サイボウズ株式会社は従業員満足度アンケートをおこない、柔軟な働き方を取り入れたことで「ワークライフバランスの改善」に成功しています。効果は歴然、28%もあった離職率が4%前後まで減少しています。「100人いたら100通りの働き方があっていい」の考えのもと、サイボウズが実践するワークスタイル変革のポイントを見ていきましょう。
<サイボウズが実践するワークスタイル変革のポイント>
- 「育児・介護」短時間勤務制度の導入
- 従業員自身が勤務時間や勤務場所を決める「働き方宣言制度」スタート
- 在宅勤務制度の拡充
- 「育自分休暇制度」開始(35歳以下の従業員は留学や転職をしても6年間復職が可能
- 副業の自由化
- 「子連れ出勤制度」スタート(やむを得ない場合限定)
柔軟な働き方や従業員目線の制度が受け入れられ、離職率の改善はもとより、従業員のモチベーションや業績の向上にもつながっています。
人事制度の改革
株式会社ディー・エヌ・エーは「シェイクハンズ」という新しい人事制度を取り入れ、従業員の能力を最適化することに成功しています。「シェイクハンズ」とは、上司の承認がなくても部署異動ができる人事制度のこと。部署異動を希望する従業員自らが、希望する部署に声をかけたり、Webサイトからエントリーしたりすることができます。そのポイントは、次の通りです。
<ディー・エヌ・エーが実践した新しい人事精度のポイント>
- 合意書をかわし合意形成できたら異動が成立
- 部署を問わず従業員への異動の呼びかけが自由
- キャリア相談室を人事部に開設
「シェイクハンズ」人事制度の実施により、次のような効果が得られています。
- スタート3カ月で20件を超える異動が決定
- 異動によってパフォーマンスが向上
- キャリア形成への意識が高まる
異動が「やりがい」を醸成し、従業員満足度は大きく向上しています。
従業員満足度アンケート(ES調査)よくある質問

最後に、従業員満足度アンケートに関するよくある質問をまとめました。
従業員満足度アンケートのメリット・デメリットとは?
従業員満足度アンケートには、次のようなメリット・デメリットがあります。
<メリット>
- 表面化していない問題の早期発見につながる
- 組織と従業員の信頼関係が構築できる
- 従業員の価値観や考え方の傾向を知ることができる
- 組織が活性化し業績や顧客満足度の向上が期待できる
<デメリット>
- アンケートに対する理解促進に時間がかかる
- 従業員の本音を引き出すアンケート設計が難しい
- 継続的に実施しなければ効果が薄い
- 回答しやすいように心理的安全性を確保する必要がある
従業員満足度アンケートを行う際の注意点とは?
従業満足度アンケートの注意点は、次の通りです。
<従業満足度アンケートの注意点>
- 実施目的を明確にする
- 回答しやすい設問を設定する
- 設問は多すぎず少なすぎず
- フィードバックを必ず行う
- 課題は必ず改善する
- 継続的に実施する
「何のために従業満足度アンケートを実施するのか」という本質的な部分を、忘れないようにしましょう。
主なアンケートの項目例とは?
従業員満足度アンケートの項目は、「全体満足度」と「領域別満足度」に分けられます。
全体満足度とは
全体満足度とは、従業員の総合的な満足度を表すものです。仕事や組織に対する「感情・態度」を可視化するアンケートの中核となる質問項目です。
例として、次のようなものがあげられます。
- 全体的に考えて今の仕事が好きである
設問に対して、5段階(そう思う・どちらかというとそう思う・どちらともいえない・どちらかというとそう思わない・そう思わない)、あるいは4段階(中間の選択肢なし)で回答してもらいます。
領域別満足度とは
領域別満足度とは、従業員の満足度を様々な領域に分けて表すものです。仕事や組織に対する従業員の「感情・態度」を可視化するもので、心理学者エドウィン・ロック教授は研究において、「仕事内容」「組織」「職場仲間」「待遇」の4つの領域に分類できるとしましたした。それぞれ、質問項目をあげてみましょう。
- 仕事内容:「今の仕事には自分の強みを活かすチャンスがある」
- 組織:「会社の経営理念・ビジョン・パーパスに共感できる」
- 職場仲間:「経営者は将来像や経営方針を詳しく伝えている」
- 待遇:「仕事内容に見合った報酬を得ている」
「領域別満足度」からは、従業員がどの部分に満足・不満足を感じているのか、また組織の強み・弱みはどこにあるのかといった、コアな部分が可視化されます。その他、従業員の要望や意見を細かく吸い上げる「自由記述項目」や、「部署・役職・勤続年数・性別」といった回答者の属性を回答してもらう「属性項目」といった質問項目があります。
従業員エンゲージメント・顧客満足度との関係性とは?
従業員満足度は「仕事や組織に対する従業員の満足度」を表す概念です。これに対しエンゲージメントは、「組織に対する『共感』や『愛着』といった従業員と組織の結びつき」を表します。また顧客満足度は、「組織が提供するサービスや製品に対して顧客がどれくらい満足しているのか」を測る指標のことです。この3つの概念には、次のような相関関係が認められています。
- 従業員満足度が高い組織はエンゲージメントが高い
- エンゲージメントが高い組織は顧客満足度が高い
従業員満足度の向上が、必ずしもエンゲージメントや顧客満足度の向上につながるわけではありません。しかし、従業員満足度が低い状態で、エンゲージメントの向上を期待するのは難しいでしょう。また、エンゲージメントの低い組織が提供するサービスや製品が、顧客満足度を高めるとは思えません。従業員満足度を向上させると共にエンゲージメントを高め、最終的に顧客満足度を向上させる意識が求められているのです。
従業員満足度を高め、エンゲージメントや顧客満足度の向上に取り組みましょう。それにはまず、組織の状態を把握する必要があります。組織の状態を把握するには、専門の調査会社が提供する「従業満足度アンケート」「エンゲージメント調査」の活用が効率的かつ効果的です。
最後に

従業員満足度アンケートを行うことで、従業員や組織の様々な状態が数値として可視化されることがわかりました。大切なことは、アンケートの結果を踏まえて課題を設定し、その課題を改善していくことです。従業満足度アンケートは、実施することが目的ではありません。実施自体が目的では「意味がない」のです。
従業満足度アンケートの本質は、従業員の満足度を向上させることにあります。従業員満足度の向上は、エンゲージメントを高め、ひいては顧客満足度の向上につながります。全ては、従業員満足度を向上させることから始まるのです。「従業員満足度アンケート」や「エンゲージメント調査」をうまく活用し、従業員満足度の向上に取り組んでいきましょう。